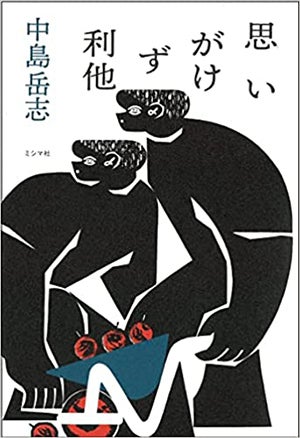中島岳志(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授)
政治学者で、仏教にも造詣の深い中島岳志氏が、先ごろ『「利他」とは何か』(集英社新書)に続き、「利他」をテーマとした『思いがけず利他』(ミシマ社)を上梓された。前作は東京工業大学リベラルアーツ研究教育院のメンバーによる共著で、多角的に「利他」をめぐる論が深められていたが、本作は中島氏の単著で利他が働く構造、利他が現象する条件などが解き明かされ、仏教の無我や縁起、親鸞の思想との深い連関が考察されている。
中島氏が洞察する利他の本質とは何か、お話を伺った。全4回に分けて配信する第1回。
第1回 利他と意思
■利他へのきっかけ──新自由主義と対峙するために
──先生は政治学者という肩書きですが、利他ということにどのようなことから関心を持たれたのかというあたりから、おうかがいできますか。
そもそも新自由主義というものに対して世界はどう立ち向かうのかということに、政治学者として関心を持ちました。通常、政治学では新自由主義に対して「大きな政府論」を考えます。新自由主義になると官から民への規制暖和で、どんどんマーケットに任せていく。行政サービスを積極的に小さくしていき、その代わり税金は安くなる。そのように個人化していくのが新自由主義です。しかし、それがいけばいくほど貧困の問題が出てきて、格差が深刻になる。それが現代社会ですよね。
そのなかで2009年に民主党政権ができて、私も若干近いところにいましたが、セーフティネットを整えていこうという議論になりました。それともう一つ民主党政権では「新しい公共」という議論がありました。これは、国家や行政サービスだけが厚いのではなくて、たとえば寄付とか、あるいはボランティアとか、そういったものが分厚い、みんなで支えあう社会をつくっていかなくてはいけないという議論でした。
特に鳩山内閣の頃に強くなりましたが、寄付した人の税制を優遇する政策をとったのです。「インセンティブを与えるから、どんどん寄付してくださいね」ということですよね。それで、どうなったかというと、寄付は全然増えませんでした。つまり、人がだれかに寄付をするとか、援助をしようとするとき、金銭的なインセンティブや功利的なことでは動いていないということです。寄付とかボランティアとか、そういったものが分厚い社会にするには、どんな動機付けが有効なのか。
そこで大きなヒントになるのが、宗教的な動機付けです。民主党政権は宗教的なことは全く理解していませんでした。
僕はインドに長くいました。インドの社会はヒンドゥー教のダルマ(dharma法、義務)という概念が非常に強いです。それからイスラム世界もインドの中では大きかったのですが、その場合ワクフ(vakıf)があります。ワクフは財産を基金として供出して、その利益を慈善事業にあてるシステムです。そのように宗教を中心とした貧困対策が行われていました。もう一つ私が経験したのはアメリカ社会ですが、ここでは貧困対策に教会が非常に大きな影響を持っています。
つまり社会的再配分の動機付けとして、宗教的な動機付けは非常に大きい。でも、それがものすごく希薄な日本社会において、どうすれば社会のなかで助け合いができるのか。それが、そもそも私が利他に関心を持ったきっかけです。
──政治学者としての論点とインドでの宗教的な知見が重なってきたことで、利他への関心が生まれたということですね。
僕の研究自体が、政治学のなかでも変わっています。行政制度とか、行政のあり方とか、選挙システムを研究するのが政治学の花形なのですが、僕自身はそちらのほうには関心がなくて、人間の精神と政治の関係を専門としてやってきました。たとえばナショナリズムとか、原理主義の問題です。あるいは、なぜ「愛国心」や「信仰心」など「心」のつく問題が政治を大きく動かすのか。それが排外主義など21世紀の最大のトラブルの元になっています。
そのように、人の心と政治の問題をどう解いていくのかが僕の研究のテーマです。利他はそこに触れてくる問題でした。
■与格構文
──先生は新刊『思いがけず利他』のなかで、利他というものは、「意思の外側」という表現をされています。私たちの生きている世界の外側に原理を求めていることだと思います。これは宗教的にはまったく問題のない話ですが、一般常識のなかで語る言葉としては難しいと思います。その辺はどのようにお考えですか。
そうですね。僕もどう語るかと考えたのですが、その中でヒントとなったのはヒンディー語の文法の与格です。
僕は19歳で大阪外国語大学に入りました。今は大阪大学の外国語学部になっていますが、そこのヒンディー語を専攻しました。実は、ヒンディー語を学びたかったのではまったくないんですよ。当時、予備校でつきあっていた女の子がどうしても大阪外国語大学でインドネシア語を勉強したいと言っていて、それなら僕も一緒に同じ大学でインドネシア語を学ぼうとしたら、「それだけは嫌だ」と言うんです。それで、インドネシアのネシアを取って、インドで話されているヒンディー語にしました。恥ずかしいのですが、これが選んだ理由です。昔は「核問題に関心があった」とか言っていましたが、正直に言わないといけないと思って(笑)。
そのような理由で選んだので、入ってすぐ留年しました。ともかく外国に興味がない、語学に興味がない、インドにも興味がない。それなのに外国語大学に入ったので、何も興味を持てずに、ヒンディー語のデーヴァナーガリー文字も覚えられない。それで留年しました。
その年が1995年です。この年は、オウムの地下鉄サリン事件、阪神淡路大震災、戦後50年と、大きなことがどっとやってきた年でした。留年で、あまりにも暇なので世の中について考えたというのが政治に関心を持つようになった始まりです。
とはいえ、いやいやながらヒンディー語の勉強もしていましたが、一番厄介だったのが与格という文法です。ヒンディー語には主格と与格の違いがあります。日本語だとほとんど「私は」と主格で始まりますが、ヒンディー語には「私に」で始まる文法があります。どんなときに主格を使い、どんなときに与格を使うかが厄介で、学校の先生は「自分の意思による行為が主格で、外部によって促され起動する行為には与格を使う」と教えます。
たとえば「私は嬉しい」は「私に嬉しさが留まっている」という言い方をします。アイラブユーも「私はあなたを愛している」ではなくて、「私にあなたへの愛がやって来て、留まっている」といった言い方をするわけです。あなたのことを愛そうとして愛したのではなくて、あなたへの愛がやって来たんだ、不可抗力なんだ、ということですよね。「なるほど」と思いました。なかなかロマンチックですよね。
風邪をひいたときも「私に風邪が留まっている」と与格を使います。そうですよね、風邪をひきたくてひくわけではないので。今はインドもパンデミックで大変ですが、コロナにかかったときも与格を使います。
その後、大学院ではインド政治を研究しました。現地調査で出かけたインドでは「君はヒンディー語ができるのか?」とよく聞かれましたが、そのときは与格を使い「あなたにヒンディー語がやってきて、留まっているのか?」という言い方になります。
なぜ、与格構文を使うのか考えたときに、言葉とか、喜びとか、愛はどこから来るのかという問題に突き当たりました。それがどこからやって来るのかというと、インド人の感覚でいえば「神」です。神からやってきて人間を動かしているというインド人の世界観が、この文法構造の中に非常に強く現れています。
これは、日本語にも色濃くあります。「私には思える」と言ったりしますよね。もともと、世界の文法の古層は与格が中心でした。これをハッキリ書いているのが『中動態の世界』の著者の國分功一郎さんです。
それで、「思う」というのはどういう現象はなんだろうと考えていくと、自分の意思によって思いをコントロールしていないことがほとんどだと気づきました。たとえば、何か風景をパッと見たとき、何かが想起される。頬を撫でる風を感じたとき、「ああ、あのときのお母さんの……」と思い始める。そうすると、そこから思いがグルグルグルグルとまわっていく。思いって「めぐって」いるんですよね。あるいは宿ったりする。「思いが宿る」とは、よく言ったものです。だから、ひょっとすると主格のほうが幻想ではないかと強く思いました。『思いがけず利他』 (ミシマ社、2021年)
■私たちは意思を持って選択しているのか?
──そうすると、私たちは「自分の意思」では考えていないということになりますか?
「意思」とはなんなのか、という問題になりますよね。近代人は「意思を持って選択する」というけど、「意思」こそが僕たちの本質的な人間観を歪めているのではないかと思います。あるいは、僕たちが意思によって生きているということ自体が、相当程度幻想ではないでしょうか。
つまり、僕という存在の根本を見ても、意思を持って生まれてきたのではなく産み落とされているわけです。親も選んでいないし、この容姿も選んでいない。関西で生まれましたが、このどうしょうもなく関西人であることも選んでいない、自分ではなにも選んでいません。大阪に生まれたくて生まれてきたわけじゃないし、親には感謝していますし大好きですけど、彼らの子どもに生まれたくて生まれてきたわけではありません。
そうすると、私をいろんな意思に還元して世界観を構築しているという近代の人間観のほうが、圧倒的に狭いのではないでしょうか。むしろ、「私に訪れて、私を突き動かすもの」のほうにこそ大切なものがあるし、僕たちは本当はそのことを知っていると思うんですよね。そこに目を向けたとき、世界の見え方が変わってきます。僕にとって、それが仏教の縁起であると思います。
■釈迦と親鸞
──「私」や「意思」は幻想のようなものであるとして、それを剥がしてしまうとすると、その人間観、世界観は仏教の認識になっていきそうです。仏教のいう無我に接近していくように思います。
無我の「我」が非常に重要で、ここは仏教がヒンドゥー教にならなかった一番のポイントだと思います。人間の意識の最も深いところにアートマン(artman真我)が存在して、それが宇宙の摂理であるブラフマンと一体であるという「梵我一如」がヒンドゥー教の世界観です。でも、お釈迦様は「アートマンがあるというのが問題であり、その我執にみんな苦しんでいるのではないか」と批判して、無我を説いた。
でも無我なら、「それなら、ここにいる私はなんだ」と。そのときに仏教が提出するのが、たとえば五蘊という考え方です。五蘊は人間を成り立たせる五つの要素のことで、色(=肉体)・受(=感覚)・想(=想像)・行(=心の作用)・識(=意識)を指します。五蘊の結合体として私が存在し、縁によってこの結合体が毎日変わっている。だから、私は昨日の私ではなく、どんどん変容していく現象としての「我」が存在しているとしかとらえられない。これが「無我の我」ですよね。
ところが、大乗仏教は如来蔵思想があるので、そのあたりがあいまいになっています。すべての有情に仏性がある、生まれながらにすでに悟っているというと、梵我一如に近くなってしまう。それはテーラワーダ仏教と決定的に違うところです。しかし日本の仏教のなかで浄土真宗(真宗)は、テーラワーダに一番近いと思います。親鸞は生きている私がそのまま仏性を持っているというヒンドゥー教的なアートマン精神に対して、「そんなわけないだろう。だって自分はどうしょうもない人間なんだから、そんな人間がそのまま仏になるのは不可能ではないか」と考えていました。
でも大乗仏教なので、だれでも成仏しないといけない。だから死後浄土しか言わないんですよ。亡くなった後にお浄土に行って、そこで仏になる。親鸞は生きている人間のなかに如来の種があって、それが開花して生きたまま仏になるなんて言えませんでした。
それが親鸞が原始仏教に近いところです。人間がそのまま仏性を持っているというのは、ヒンドゥー的な精神ですから、ヒンドゥー教の前身であったバラモン教を批判する御釈迦様の視点に日本仏教のなかでは最も近いです。だけど、だれでもが成仏しなくてはいけないから死後浄土と言う。親鸞はここのせめぎ合いを一番苦労して、そう考えたのだと思いますね。
■業の二重の働き
僕はヒンドゥー教における業は嫌だなあと思っています。仏教の業でも、特に僕が影響を受けた親鸞という人は、業は二重のものと考えています。人間の業と同時に、仏の業というのがあるというのが、彼が言わんとした「大願業力」です。業は、私たちのどうしようもないものだけでなく、阿弥陀仏にはどうしてもみんなを救ってしまうという業があります。
──なるほど、「仏の業」というと、そこには業を生んだある意思が存在していることになりますよね。
だから、人間が意思を持って行為をコントロールしているというのは、究極的には幻想なんですね。仏様はある種の主体的な意思ではなく、それも仏の中にある業なのですね。仏は仏で、業によりどうしようもなく救ってしまう。それはどこからか流れてくる根源的なもので、仏は意思すらなく他者を救ってしまうんですね。
(つづく)
2021年11月4日 zoomにて
取材、編集:川島栄作(サンガ新社)
取材、構成:森竹ひろこ(コマメ)第2回 利他が宿る器になるとき

![中島岳志「なぜ今、利他なのか」[1/4]](https://image.osiro.it/pass/main_images/140257/images/original/%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E5%B2%B3%E5%BF%97-1-4.jpg?1638424527)