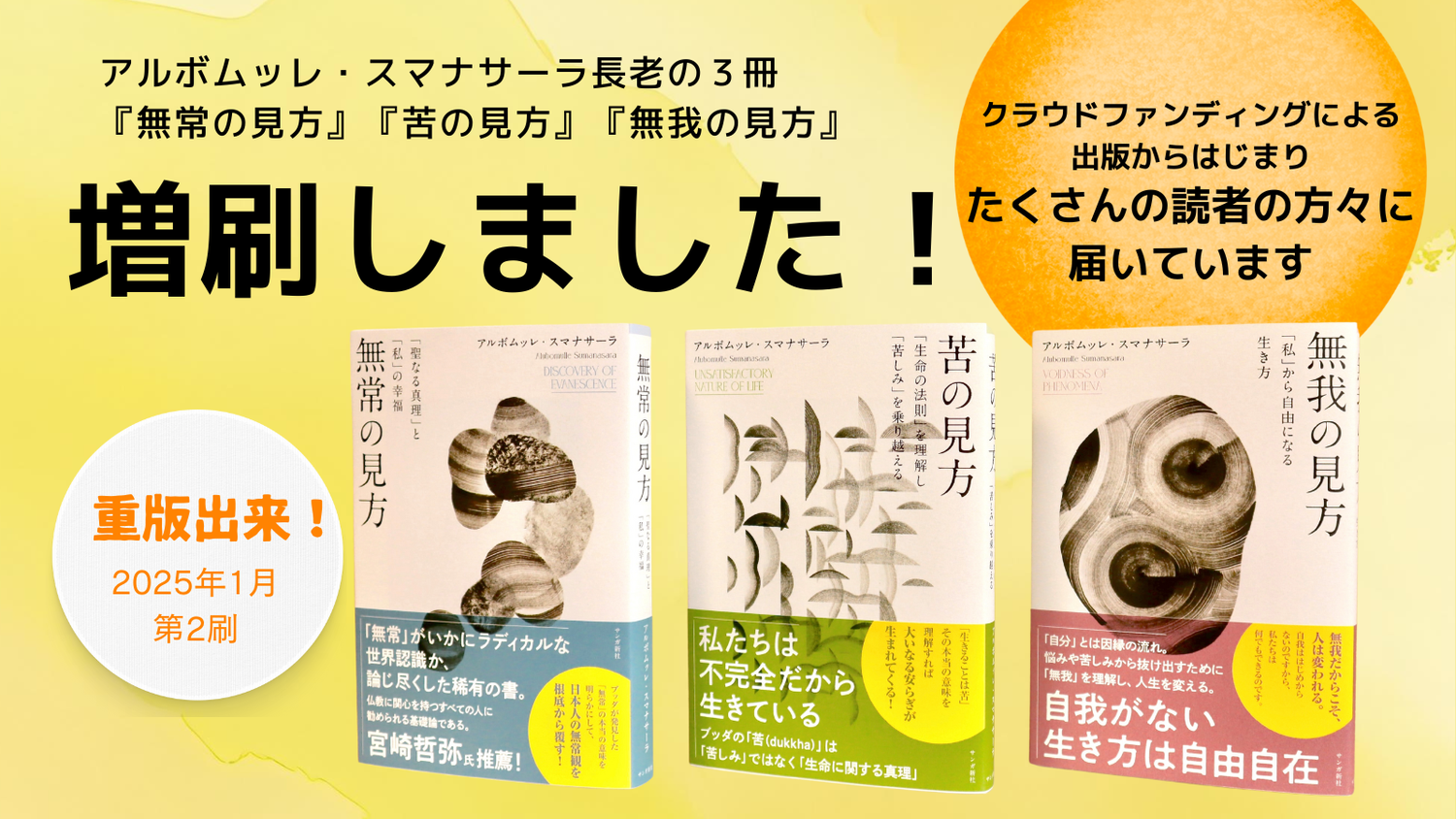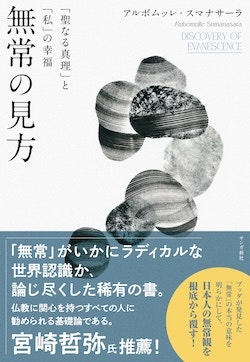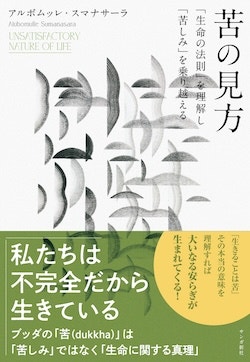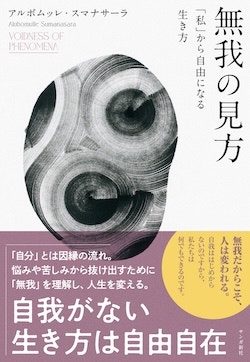アルボムッレ・スマナサーラ(初期仏教長老)
サンガ新社は、アルボムッレ・スマナサーラ長老の著書『無常の見方』『苦の見方』『無我の見方』を2023年11月に刊行しました。本書の刊行を記念し、2024年1月16日、スマナサーラ長老に「無常」「苦」「無我」のポイントを教えていただきながら、一緒に読み深めていくオンラインセミナーを開催しました。仏教の最重要語である「無常」「苦」「無我」の3つの繋がりを理解していきましょう。
第4回 質疑応答
■質問1
──変化に逆らいたくなるのは、安定する方向に認識(心)が働くからでしょうか。また、その認識(心)の働きに気付くことが覚りの入り口なのでしょうか?
スマナサーラ 心というのは認識するものです。しかし認識そのものがすごく変なんです。純粋にものを認識しないのです。
たとえば認識して執着の感情が作られると、それをなんとかして実現しようとします。これは心の問題です。心はありえないことをやろうとするのです。
心は正しく認識せず、主観で認識します。いつでも主観で認識して、ありのままに認識しない。
だから仏教では「ありのままに、あるがままに見なさいよ」と言うのです。あるがままに見るとは「客観的に見る」ということです。
でも皆様、どうもあるがままに見るのは嫌なのですね。
日本の文化に生け花というものがありますけど、生け花の先生たちは苦しみのいい例です。
花を生ける先生方は、ないものを作っちゃうでしょ? 放っておけばいいのに、心がいろいろな形の花や枝や葉っぱを見て、「じゃあこう組み立てましょう」と幻覚を作ろうとする。
心が自分の希望通りに宇宙を変えようとするのです。花を生けるというのは、自然を変えようとしてやることでしょ? だからいろいろ苦しいんですよ。生ける器を選んだり、いい置き場所を考えたり。置く場所によっても美しく見えたり、そうじゃなかったりしますからね。だから、そんな楽じゃないんです。
家を作ったり建物を作ったり、携帯電話を作ったりするのだって楽なことではありませんよ。すべて自然法則に逆らおうとしていることですから。
でも、逆らえないんです。我々が使っている携帯電話も宇宙法則に従って作っています。素粒子の流れを知って、どこをいじれるかとチェックして、工夫すると電子の流れが変わると自然界から学んで、それで作っているんです。
まあ、そんな感じで、前半の質問の答えとしては、安定する方向というか、自分好みの認識にしようとすることが生きることだから、生きることは苦なのです。
後半もその通りですね。「ああ、こんなふうに認識が起きているんだ」とありのままに観察することが、覚りに入る道になります。その実践法は皆様知っていると思います。
■質問2
──『苦の見方』の5ページに、次のように書かれていました。
「三相を経験的に発見して理解するという偉業に挑戦する前に、知識を駆使してガイドライン程度の理解をすることは必要になります。私たちの知識を駆使して日常の経験に基づいて理解できる「苦」もあるのです。それは三相の苦ではなく、四聖諦で説かれている苦です。ですから本書では、三相の苦ではなく、四聖諦で説かれている苦を説明することにしました。」
三相の苦と四聖諦の苦の違いを教えてください。
スマナサーラ 三相の苦と四聖諦の苦はアプローチが違います。三相の苦というのはすごく難しいんですよ。存在すべてをまとめて見ることですから。たとえば宇宙について、いろいろな方法で調べることはできますが、宇宙のすべてを知ることはできませんね。だからそんなことを調べるのはやめなさいとお釈迦様はおっしゃっています。命は短いですしね。
一方、四聖諦の苦は俗世間的に言う「私の問題(my problem)」です。自分の生き方(my life)を見ると、そこに苦を発見する。苦があるから頑張っていることがわかる。でも頑張っても苦は消えない。変化して、変化して、変化し続けますから。
生まれること、老いること、病気になることは苦です。
なぜ生まれることが苦なのか。なかったものがいきなり生まれちゃうと大変なんですよ。今年も地震が起きました。それによって、それまでなかった状態が生まれて大変な苦が生じましたね。
子供が生まれても大変ですよ。「ご出産おめでとうございます」と言われても、お母さんが赤ちゃんにきちんと対応できないと、世間から育児放棄と言われてしまいます。
瞬間瞬間、新しい現象が生まれるけれども、心は変化せずに昨日と同じ状態でいたいと思う。それですごい苦しみが生じてしまうのです。
老いること、病気になることも大変です。周りの人々が亡くなっても、すごく悲しくて、苦しみを感じます。
希望通りにいかないことが、あれこれ起きて、ずっと苦しみを実感しながら、その連続で我々は生きているのです。
生老病死や愛別離苦、怨憎会苦、それらを全部まとめたものが四聖諦の苦です。自分の身体に対する執着、感覚や思考に対する執着、そのような、自分が経験できる苦ですね。
一方で三相の苦は、経験できるかできないかよくわかりません。まあ、知識系の人々は三相の苦を理解しても構いませんけどね。
■質問3
──三相はわかったつもりですが、自分が覚っていないことは間違いありません。だから本当にわかっているわけではないのだと思います。しかし、ここからどうやって次に進めばよいのかがわかりません。
スマナサーラ なるほど。じゃあ、「真理はこうなのに、自分の心は逆らおうとしているじゃないか」とチェックしてみてください。生きることは逆らうことですから、逆らったところで別にどうってことはありませんが、そのたびに「ああ、逆らうと苦が生じるんだ。逆らうと怒り、嫉妬、憎しみが生じるんだ。実際は無常・苦・無我であるのに」というふうに、自分の心に生まれる矛盾に気づいてみてください。毒だと知っているのに食べたくなるような、その矛盾ですね。
日本語でも「わかっちゃいるけどやめられない」と言いますね。それに気づいてみてください。
■質問4
──ご法話の中でヴァイオリンのたとえが出てきました。「ヴァイオリン=眼耳鼻舌身意」「弦=色声香味触法」「音=認識=ただの波」ということでしょうか? 「心=認識」もただの波動なのかなと思いました。
スマナサーラ ご自分の分析だから、それはそれでけっこうです。ただ、憶えておいていただきたいのは、たとえ話というのはアバウトに理解すればいいものだということです。1つの現象を分析して見せただけで、別に1つの現象ですべてを説明しようとしているわけではありません。
おっしゃる通り「心=認識」は、ただの波動です。
■質問5
──無常・苦・無我の真理に対して心から納得し、逆らう気持ちがまったくなくなるのが心の平安なのでしょうか?
スマナサーラ そうですね。「無理なことはしません」という感じです。
お釈迦様は「覚った人は、やるべきことをやり終えた。なすべきことをなし終えた」とおっしゃいました。もう心が安心して平安で、安穏になっちゃうんです。
覚った人も肉体がある場合は肉体を維持管理しますけど、他の人みたいに苦しんだり、大変だと思うことはありません。お腹が空いたから何か入れます、疲れたから座ります、という感じで。
ですからおっしゃる通りです。逆らう気持ちがまったくなくなると、楽になるのです。
(完)
2024年1月16日 zoomにて開催
『無常の見方』『苦の見方』『無我の見方』刊行記念オンラインセミナー
「アルボムッレ・スマナサーラ長老と『無常の見方』『苦の見方』『無我の見方』を読む」
構成:中田亜希
第3回 悪循環からの脱出
お知らせ
人生を変える3冊を増刷しました!
サンガ新社では、2023年にクラウドファンディングを通じて復刊したスマナサーラ長老の著書 『無常の見方』『苦の見方』『無我の見方』の3冊を、2025年1月に増刷しました!
各書籍のAmazon販売ページを以下にご紹介しますので、ぜひお読みになってみてください。
『無常の見方: 「聖なる真理」と「私」の幸福』
『苦の見方: 「生命の法則」を理解し「苦しみ」を乗り越える』
『無我の見方: 「私」から自由になる生き方』

![アルボムッレ・スマナサーラ「アルボムッレ・スマナサーラ長老と『無常の見方』『苦の見方』『無我の見方』を読む」[4/4]](https://image.osiro.it/pass/main_images/475202/images/original/sansou1.png?1746331697)